
コラム
建築図面の記号と意味を建築設計のプロが分かりやすく解説

建築図面に描かれる記号は、建物の設計情報を正確に伝えるための重要な要素です。窓やドアの開閉方向、設備の配置、構造材の種類など、建物に関する様々な情報が記号によって表現されています。
設計者から施工者へ、そして維持管理に至るまで、建築のプロフェッショナルたちはこれらの記号を共通言語として使用しています。この記事では、建築設計の実務で使用される記号の基本から応用まで、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
建築図面の記号とは何か

建築図面の記号は、建物の設計情報を正確に伝えるための大切な要素です。これらの記号は建物を建てる際の約束事として、設計者と施工者の間で共通の理解を深める役割を果たしています。
建築図面で使われる記号の基本的な役割と重要性について
建築図面の記号は、図面上で建物の様々な情報を表現するために使われています。例えば、窓やドアの位置、開く方向、電気のスイッチやコンセントの場所など、建物に関する多くの情報を記号で表現しています。
一つの図面には数多くの情報が詰め込まれており、それらを文章だけで説明するのは難しいため、記号を使ってわかりやすくしているのです。このように記号を使うことは、建物の情報を正確に伝える上で大変重要な意味を持っています。
設備の位置を示す記号は、工事を行う際の重要な指示となります。
建築図面の記号が標準化されている理由と利点について
建築図面の記号は日本全国で統一されているため、場所が違っても同じように理解できます。建築の現場では、様々な職種の人々が関わって作業を進めますが、標準化された記号があることで、共通の理解のもとで効率的に作業可能です。また、設計者が変わっても一貫した表現が可能となり、プロジェクトの円滑な進行を支えています。
建築図面の記号の種類と使い方
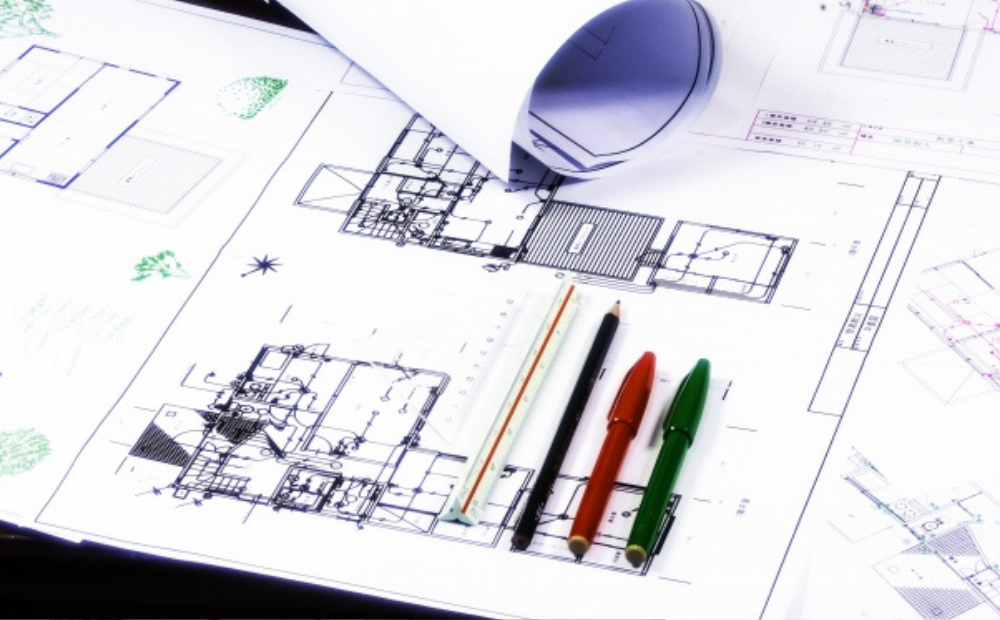
建築図面には様々な種類の記号があり、それぞれ建物の部分や設備を表現するために使われています。窓やドア、住宅設備、構造材、電気設備など、建物を構成する要素ごとに専用の記号が定められています。
以下の図は、建築図面でよく使用される基本的な記号の例です。記号を組み合わせることで、建物の様々な情報を図面上に表現することができます。
これらの記号は、建築図面を読み解く上での基本となります。それでは、各記号の具体的な使い方について詳しく見ていきましょう。
窓やドアなど開口部に関する建築図面の記号について
窓やドアの記号は、建築図面の中でも特に重要です。同じ窓やドアでも、開閉の方法によって異なる記号で表されます。たとえば、横にスライドする引き違い窓と、外に開く開き窓では、異なります。また、ドアについても同様に、開きドアと引き戸では異なる記号で表現します。
これらの記号は、実際の建具の動きを表現しており、図面を見る人は記号から建具の使い方を理解することが可能です。また、建具の大きさも図面上では実際の寸法に合わせて描かれるため、スペースの確認にも役立ちます。
住宅設備機器に関する建築図面の記号について
住宅の設備機器には、それぞれ専用の記号が用意されています。浴室、トイレ、キッチン、洗面台などは、上から見た形に近い記号で表現されます。浴室の記号では浴槽の位置や形、トイレの記号では便器の向きがわかるように描かれています。
キッチンの記号では、流し台やコンロの位置も正確に示されます。洗面台の記号も、実際の形状に近い記号が使われます。これらの記号は、機器の大きさや設置位置を正確に表すために重要です。設備機器の記号は、給排水や電気の配線計画とも密接に関係しているため、建物全体の設備計画を理解する上で欠かせない情報となっています。
構造材に関する建築図面の記号について
建物を支える構造材にはそれぞれ定められた記号があります。柱は「C」、大梁は「G」や「B」、小梁は「b」、床は「S」という記号で表されます。また、耐震壁は「EW」、基礎は「F」という記号が使われます。たとえば「2C1」という記号は、2階にある柱のことです。
これらの記号は左から右へ、下から上へと順番に数字が振られていきます。構造材の記号は建物の構造を理解する上で特に重要な情報です。これらの記号の意味を正しく理解することは、建物の構造を把握する基本となります。
電気設備に関する建築図面の記号について
電気設備の図面では、スイッチやコンセント、照明器具などを表す専用の記号が使われています。照明器具の記号は取り付け方によって異なり、天井に直接つける照明と天井に埋め込む照明では違う記号が使われます。
コンセントの記号も一般用と専用回路用で異なります。また、分電盤という電気の制御装置の位置も、専用の記号で示されます。電気設備の記号には、その位置だけでなく、スイッチがどの照明を操作するのか、コンセントがどの回路に接続されているのかといった情報も含まれています。
建築図面の記号の基準と規格
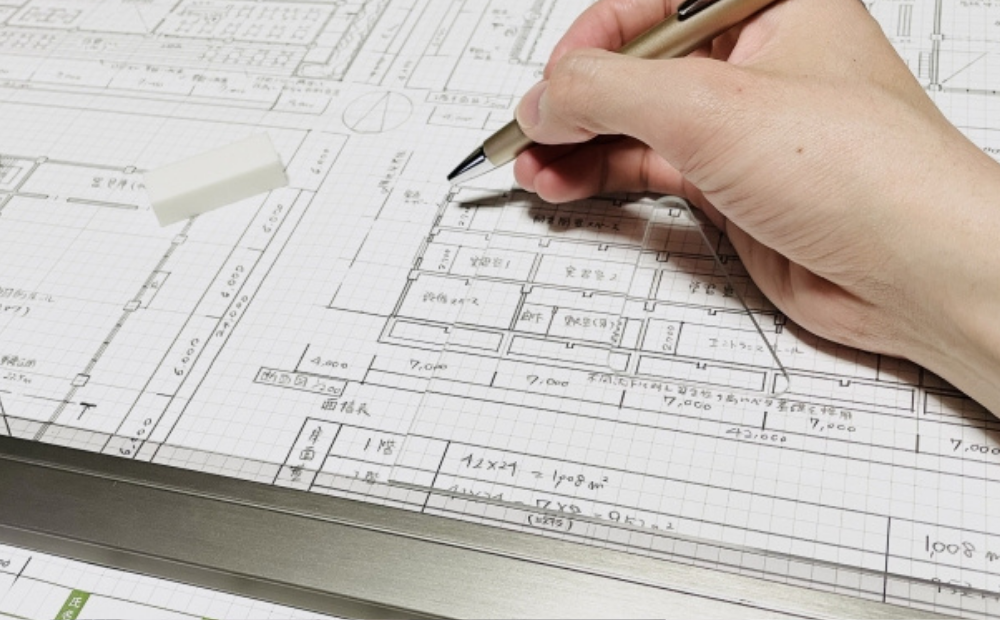
建築図面の記号には、正しい使い方のルールが定められています。このルールは日本工業規格(JIS)によって定められており、建築業界全体で守られています。
JIS規格に基づく建築図面の記号の種類と表記方法について
建築図面の記号は、JIS A 0150(建築製図通則)という具体的な規格に基づいています。この規格では建具や設備、構造材など、各要素の記号の形状や大きさが細かく定められています。また、材料表現の方法や縮尺による表現の使い分けなど、実務に即した具体的な基準が示されています。
建築図面の記号における寸法と単位の表示方法について
建築図面では、長さを表すときにはミリメートル(mm)という単位を使うのが基本です。もし他の単位を使う場合は、センチメートル(cm)やメートル(m)という単位を必ず書き添えます。
建物にかかる力の大きさを表すときには、ニュートン(N)という単位を使います。以前は重さの単位であるキログラム重(kgf)が使われていましたが、現在は国際的な基準に合わせてニュートンが使われています。
図面の中で使う単位を間違えると、建物の大きさや強度に大きな影響が出てしまいます。そのため、単位の表示は特に注意深く確認することが重要です。正しい単位を使うことは、建物を安全に建てるための基本となっています。
まとめ
建築図面の記号は、建物を正しく建てるために欠かせない重要な情報です。記号は建物の形状や大きさ、設備の配置、構造強度など、多くの情報を正確に伝えるために使われています。
JIS規格によって標準化された記号を使うことで、異なる場所や関係者間でも同じ理解のもと作業を進めることができます。窓やドア、設備機器、構造材、電気設備など、それぞれの要素に対して専用の記号が定められており、これらを適切に使用することで建築図面は正確な情報伝達ツールとなります。
1967年の創業以来、橋梁設計を中心に実績を重ねてきた国土工営コンサルタンツ株式会社では、BIM/CIMを活用した3Dモデリングなど、最新技術と豊富な経験を活かした設計サポートを提供しています。橋梁や道路設計、構造物の点検調査から補修・補強設計まで、専門的な技術で対応いたします。
